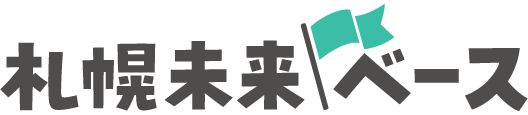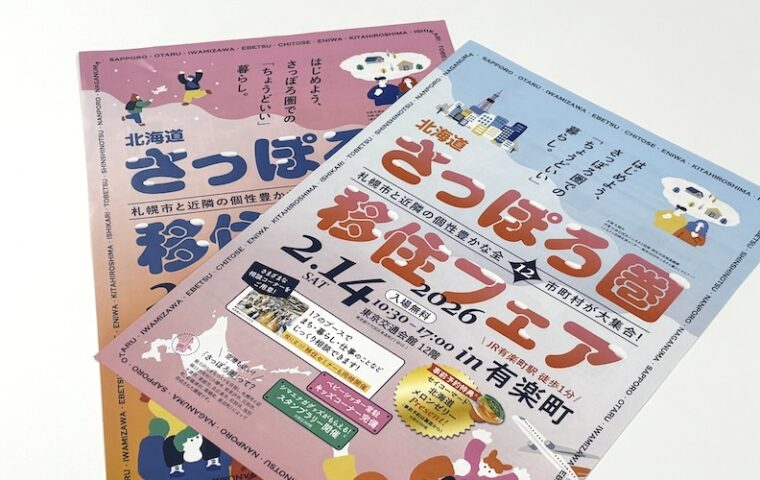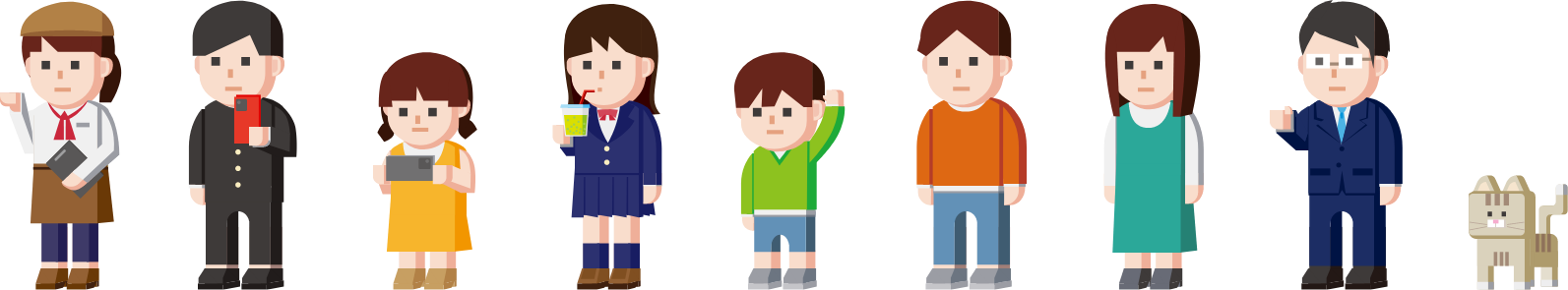「在宅医療」や「緩和ケア」という言葉、聞いたことはあるけれど、その意味や内容はよく分からない…。家族や自身がそれを利用していなければ、大半の人がそうなのではないでしょうか。病気になったら病院へ、そして最期も自宅ではなく病院で。いつの間にかそれが当たり前のようになっていますが、本当は自宅で療養したり、最期のときを家族と過ごしたりすることも、選ぶことはできるのです。もちろん、場合によっては設備の整っている病院へ入らなければならないこともありますが、それでも選択できる可能性は0%ではありません。今回、取材に伺ったのは、在宅医療を支える訪問診療と緩和ケアを行っている「巡る診療所」。国道5号沿いの看板には、「訪問診療」「緩和ケア」の文字、そしてドクターがおうちを訪問するかわいいイラストが大きく描かれています。早速、院長の飯田智哉さんに開業までのことや訪問診療への想いなどを伺っていきましょう。
一般への認知がまだ低い「在宅医療」
札幌市のホームページによると、在宅医療とは「自力での通院が困難な場合や住み慣れた自宅等の生活の場で医療を受けたい場合に、医師などが自宅等を訪問して看取りまでを含めた医療を提供するもの」とあります。ひとりの患者さんに対して、訪問診療の医師をはじめ、ケアマネージャーや訪問看護師、ヘルパー、医療ソーシャルワーカーなどさまざまな職種の人たちが連携し、チームとなって支えるそう。

調べれば調べるほど、知らないことだらけだと実感させられますが、そもそも「病院は混んでいる、待たされる」というイメージを抱きがちな一般人としては、訪問診療を担う医師やクリニックの数自体、まだまだ少ないのでは?と思ってしまうのですが…。
「札幌市内でいえば、10年前と比べると訪問診療のクリニックはだいぶ増えています。患者さんや一般の方たちにも少しずつ認知されてきていると思いますが、実のところ利用率は低く、サービスは飽和状態にあります。だからこそ、もっと在宅医療や訪問診療についてたくさんの方に知ってもらいたいというのが僕の思いです。在宅医療というのは、本当におすすめしたい医療の形のひとつなので」
「巡る診療所」の飯田智哉院長は、そう熱く語ります。飯田院長が在宅医療に携わるようになったのは、前の職場である「札幌在宅クリニックそよ風」に転職した2020年から。それまでは、内科医、消化器内科医として大学病院やその関連病院に勤務していました。

「最初から在宅医療に興味があったわけではないんです。大学院を出たあと、医者としてどうやって生きていこうか考え、転職活動をしていたときに、エージェントの方から勧められたのがきっかけでした。『そよ風』の現場を見学させてもらったとき、患者さんの症状だけでなく、患者さんやご家族の気持ちに寄り添った医療を提供している医師の姿を見て、自分が本当にやりたかった医療はこれだったと気付かされたんですよね」
原点に立ち戻り、「札幌在宅クリニックそよ風」で在宅医療に取り組みはじめた飯田院長。次は、そもそもなぜ医者になろうと思ったのか、そして、「巡る診療所」開業までの歩みについて伺っていこうと思います。
幼少期の医師のイメージは「町医者」
小樽出身の飯田院長は双子の兄。弟も医師で、小樽で小児科クリニックを開業しているそう。兄弟で医者ということは、親や親せきに医療従事者がいるのかと思いきや、「いや、医療関係者はいないんですよ」と首を振ります。

「もともと、弟が幼いころから将来は医者になると言っていたんです。彼はその夢をずっと言い続けていて、高校に入ったころ、弟に感化されて僕も大学の医学部を目指すことにしたんです。弟は、僕たちが通っていた小児科の先生に憧れていて、あんな先生になりたい!という強い思いを持ち続けていました。僕もその先生のことは好きで、病気で診察に行くんですけど、先生に会うと心が温かくなって、病院に行くのが好きだったんですよね」
その医師は、小樽の三ツ山病院の小児科医で、龍宮神社の宮司でもある本間公祐先生。小児科医ではありますが、高齢者医療などにも携わり、また宮司として地域とのつながりもある医師で、「なんでも診る町医者のような方で、そのころ、僕の中で医者といえば本間先生のような町医者というイメージだったんですよね」と振り返ります。
「弟は現役で合格したのですが、僕は1年浪人して札幌医科大学へ。弟は小児科と決めていましたが、僕は幅広く診られる医者になりたいと思って、1年生のころから第一内科に進むことを決めていました。今は細かく分かれていますが、当時の第一内科は消化器、血液、膠原病など幅広く診察ができる医局だったんです」

地元の小樽市立病院や市立室蘭総合病院といった関連病院で、消化器内科医として臨床の経験を積み、5年経ってから札幌医科大学大学院へ。医師の中には、臨床の現場で力をつけたあと、大学院へ進む人が多く、「第一内科に所属する7割近くの医師が大学院へ進むのですが、僕も大学院でマウスを使った炎症性大腸発がんに関する研究に取り組みました。半日医師として仕事をして、半日は研究や論文作成という4年間で、寝る時間もほとんどない状態でしたが、大学院で学んだことは臨床医としても役立つもので、結果として意味のある時間だったと思います」と続けます。
ところが、大学院を卒業して医学博士になったものの、「自分がどこに進もうとしているのか分からなくなったんです」と飯田院長。「研究を続けるために海外へ留学することも考えたのですが、そもそもどうして医者になろうと思ったのかという根本的な部分で引っかかりがあって…。また同じころ、小樽で小児科クリニックを開院する準備をしている弟を見て、自分のやりたい医療や自身が考えていた医師の在り方について考えるようになりました」と話します。
「人のための医療」との出合い
悩んだ末に大学の医局を離れる決心をし、転職活動をスタート。エージェントに登録すると、担当者から「先生は在宅医療が合うと思う」と勧められます。

「それまで在宅医療と接点はなく、考えたこともなかったのですが、外来を持たない訪問診療専門の『札幌在宅クリニックそよ風』の現場を見学させてもらったとき、いい意味で新鮮な衝撃を受け、自分がやりたい医療はこれだと思いました」
病院で診察にあたっていたときは、「病気」を診ることに比重が置かれ、「治す」ことが第一でしたが、在宅医療は「治す」よりも患者さんやその家族に寄り添い、患者さんが「どうしたいか」という気持ちを優先。飯田院長は、「1人の患者さんのために、医師をはじめ、みんながチームになって動く。まさに人のための医療だと感じました」と話します。
2020年から「札幌在宅クリニックそよ風」に勤務。在宅医療専門医の資格も取得し、翌年には院長に抜擢されます。
「そよ風に入った当時は、僕を含める4名の医者とスタッフをあわせて20数名のクリニックでした。一般の人たちに在宅医療を知ってもらいたい、在宅医療に携わる人を増やしたいという思いで、一般市民向けのイベントを開催するなど、啓発活動も積極的に行いました。院長になってからは組織を大きくすることにも力を入れ、医者も10名に増やして50名以上のスタッフを抱えるようになりました」

院長になって3年、経営にも携わる管理職としての苦労や目指す医療の形との乖離などもあり、あらためて自分のやりたいことを自分の責任で行いたいと考えるようになります。
「『そよ風』では、在宅医療に関してゼロから学ばせてもらいましたし、管理職としてもたくさんのことを学ばせてもらいました。僕は、自分がこれだっ!と思ったら、すぐに動きたいタイプ。基本的に雇われるのが向いていないんですよね(笑)。ちょうど弟が2つ目のクリニックを開業するというのにも触発されて、自分が理想とする医療を提供できる自分で組織を作ろうと考え、独立を決めました」
同じ志のスタッフとともに、心を診る
出身地である小樽にも近い、手稲に診療所を構えることに決めます。「街を巡り、巡り会った患者さんやその家族の心に思いを巡らせて、全力でサポートする」という想いから「巡る診療所」という名前を付けました。
診療所のイメージカラーはオレンジで、訪問する車の色もすべてオレンジ。「元気を与えるビタミンカラーなので、患者さんにも元気を感じてもらえたらと思っています」と話します。11月1日が開業日ということで、車のナンバーは「11-01」、電話番号の下四桁も1101と統一したそう。

訪問診療の対応エリアは、手稲区・西区・北区のほか、隣接する小樽市や石狩市へも出向き、地域の医療機関との連携も大切にしています。現在、巡る診療所で診ている患者さんは居宅の方が100名ほど、近くの高齢者施設に入居している方が150名ほど。この患者さんたちを飯田院長のほか、院長の想いに賛同する5人の少数精鋭のスタッフで対応しているそう。取材時の和気あいあいとした雰囲気から、チームワークの良さが伝わってきます。
「1人2役以上の仕事をしてくれる優秀なスタッフばかりです。僕は突っ走ってしまうところがあるので(笑)、うまくそれを制御してくれるなど、バランスはいいと思います」
スタッフの皆さんが着用しているユニフォームの胸元には、メガネが聴診器をつけてハートの音を聞いているロゴタイプが刺繍されています。メガネは飯田院長を表し、ハートは心臓を診る意味かと思いきや「患者さんのハート、心を診るという意味を込めています」と飯田院長。




在宅医療を安心して受けてもらえるように
「在宅医療の本質は、『人』をきちんと診ること。患者さんの症状と共に心も診るものだと考えています。そして、在宅医療に携わる医師は『何でも屋』だと思っています。患者さんの中にはガンの方もいれば、神経難病の方、臓器不全の方など、抱えている病はさまざま。どれだけ対応できるか、医者としての能力も問われます。また、患者さんの望みに耳を傾けながら、治らない病気の症状をどうマネジメントしていくかという緩和ケアの部分も大切になります」
緩和ケアの専門性も大事にしたいと考え、昨年、緩和医療専門医の試験にも合格。この緩和ケアを含む看取りに関しては、患者さんの家族との関係も重要になってきます。そのことに関して、「残されたご家族の後悔は必ずあると思っています。ああすればよかった、こうしてあげればよかったというのはどうしてもあると思うんです」と飯田院長。「でも、在宅医療を利用することで、自宅で最期を迎えたいという患者さんの希望を叶え、少しでも穏やかに、ご家族で看取ることができたら、残された方たちの後悔を少なくすることはできると思うんです」と続けます。

「患者さんのためにも、そのご家族のためにも、本当にたくさんの方に在宅医療を知ってほしい。そして、僕自身、医師として、患者さんとそのご家族のために精一杯サポートできる在宅医療の仕事を誇りに思っています」
もっとたくさんの人に在宅医療について知ってもらいたいと、啓発のため、多忙な中、一般市民向けの講演会に登壇し、メディアへの出演も数多く引き受けています。また、医師会や学会を通じた活動にも従事。
最後に、これからやりたいことや今後の構想を尋ねると、「在宅医療を広く知ってもらう活動は続けていきたいと考えています。巡る診療所としては、組織を大きくしていこうという気はありませんが、10年後くらいには地域に根差したクリニックを作って、訪問も外来もどちらもできるようにしたいと考えています。クリニックという場所があることで、より地域の方に安心してもらえると思うので。そして、余力があれば、オンラインを駆使し、田舎に暮らす人たちの緩和ケアや医療支援も地域の関係機関と連携しながら行いたいですね」と力強く語ってくれました。
飯田院長が子どもの頃に好きだった本間先生は、何でも診てくれる町医者のような存在。在宅医療に取り組む飯田院長の今の姿と相通ずるものがあるようにも思います。「そうですね、考えてみたら共通するものがありますね。子どもの頃、本間先生のところへ行って、温かい気持ちになれたように、僕が訪問することで患者さんやご家族の方が、安心してくれたらいいなと思います」とにこやかに話してくれました。