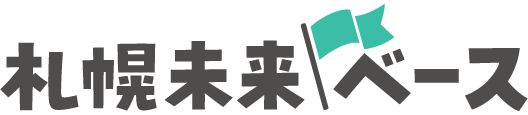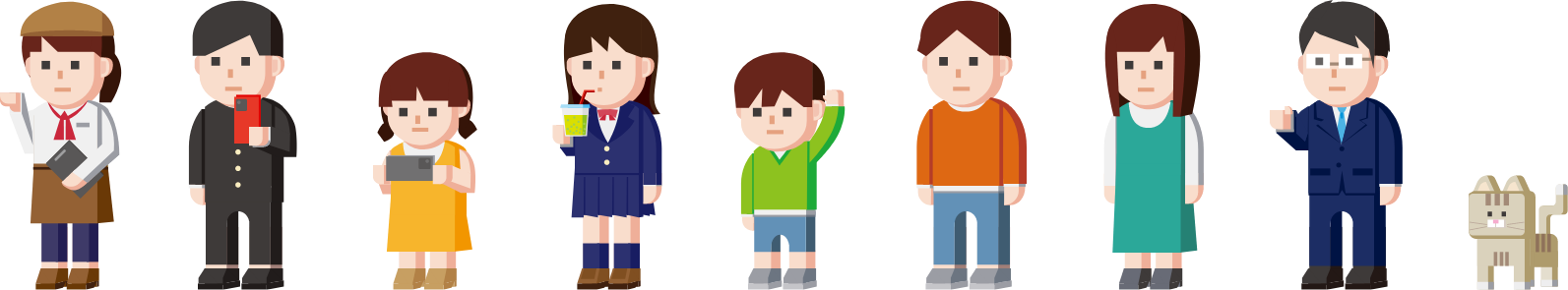創業から4代続く「野口染舗」。長年、着物の染めや洗い張りを手がけてきました。時代の流れとともに着物を着る人が減り、このまま指をくわえて見ているわけにはいかないと、かねてから危機感を持っていたのが現社長の息子で取締役の野口繁太郎さんです。
もともとは跡を継ぐつもりもなかったという野口さんですが、現在は5代目としての自覚を持ち、着物文化に新しい風を吹き込み、さらに北海道の素材を用いた染色ブランドも立ち上げました。今回は、野口さんのこれまでの歩みとこれからの挑戦について伺いました。
海外で着物のことを何も語れなかった恥ずかしさと悔しさが家業を継ぐきっかけ
豊平川にかかる東橋から500mほど入った菊水エリアに「野口染舗」があります。創業は昭和23年(1948年)。もともと京都で悉皆屋(しっかいや)を営んでいた初代・野口繁雄さんが新天地・札幌で染色業を行う「野口染舗」を開業したのが始まりです。ちなみに悉皆屋とは、染めをはじめ、着物のお直しに関する相談をすべて受ける窓口であり、染めや仕立てなどそれぞれの職人を取りまとめるプロデューサー的な存在のことを言います。
今回お話を伺う野口繁太郎さんは創業者である繁雄さんの孫にあたります。4代目である現在の代表・聡さんは野口さんの父親です。父の背中を見て育ちましたが、サッカーに夢中だった10代のころは跡を継ぐことを考えていなかったと言います。
そんな野口さんに転機が訪れたのは、海外を旅した20代前半でした。6カ月のオーストラリアの滞在や、1カ月のアメリカ横断の旅を通じ、世界の人々と交流を深めた際、「日本人は毎日キモノを着ているんでしょ?」と尋ねられたのがきっかけとなりました。

「当時、日本から来た言うと、みんながスシ、キモノって話しかけてくるんです。でも私自身は家業が着物に携わっているにも関わらず着物を着られなかったし、着物について何も知らなかったんです。自国の文化、家業について答えられなかったことがとにかく恥ずかしく、悔しいって思いました。今でもそのときの思いは忘れられません」
サッカーに打ち込んでいたときに培われたハングリー精神が、ここでムクムクと頭をもたげ、アメリカを横断している最中に跡を継ぐことを決めたと言います。
「特に父親から跡を継ぐように言われたことはほとんどなかったのですが、それまでいろいろな言い訳をしながら私自身が跡を継ぐことから逃げていたのかもしれませんね」

帰国後、父の聡さんに「跡を継ぎたい」と申し出、その際、ほかの社員と同様に履歴書を提出し、入社試験を受けて入社します。
「息子だからという甘えは捨て、きちんとイチから着物について学ばせてもらおうという気持ちでした」
着物の世界は想像以上に奥が深かったと言います。着物ができ上がるまではさまざまな職人たちが関わることをはじめ、基本的なデザイン(形)が同じなので洋服に比べて流行に大きく左右されないこと、色や柄、帯との組み合わせなどでおしゃれが楽しめること、染め替えや洗い張りなど手入れをきちんと行うことで長く着られるものであることなどを学びます。また、着物を着る人たちの気持ちも理解したいと着付けも習得。それと同時に、着物を着る人が減っていることや着物業界の行く末についても考えるようになります。
このままではいけない。危機感から生まれたデニムの着物やJUBAN Tシャツ
時代の流れとともに着物業界も変化を余儀なくされます。野口染舗はそれまで法人との取引がメインでしたが、昭和の終わり頃から思い切って個人からの受注も請けることに。
「父の代から始めたのですが、業界の風穴を空けるような思い切った挑戦だったと思います。当時は今に比べると着物を着る方がまだ多かった時代で、お客さまもたくさんいらしていました」
しかし、野口さんはこのままでもいけないと感じていたそう。顧客の多くが60代、70代と高齢化しているのは明らかで、さらに着物自体が高価なものという位置づけになり、若い人たちが手に取りにくい状況であることに危惧を覚えたと言います。

野口さんは、自分と同世代や若い人たちに向けてどうやって着物文化を広め、伝えていけばいいかを考えます。従来のように反物を購入して着物をあつらえるとなると、なかなか手が出ないのが現実。それであれば、洋服感覚で普段から気軽に着られるものを作ろうと、2011年から野口さんはデニム生地を使った男性向けの新しい着物の製造販売を始めます。
手探りでスタートした「着流しデニム」は、2013年に「Shi bun no San」(シブンノサン)というブランド名でさらなるステップアップを目指すことに。東京の大手百貨店にプレゼンし、イベントやポップアップで販売の機会を設けてもらうようになります。マーケティングも兼ね、野口さんは自ら店頭にも立ちました。
「最初は歴史の浅い北海道の人間が着物について何を語れるんだというような目で見られることもありました。正直悔しい気持ちもありましたが、とにかく結果さえ出せば認めてもらえるだろうと思って必死でしたね。最初に立たせてもらった伊勢丹の新宿本店では、いろいろなことを学ばせてもらいました。とにかくたくさんのお客さまがいらっしゃるので生の声を拾えるのはもちろん、商品のディスプレイやブランディングなど得るものがたくさんありました」


最初の頃は、百貨店の開店時間から閉店時間までずっと店頭にいたこともあったそう。そんな一生懸命な野口さんの姿を見ていた人たちに本気度が伝わり、周囲からも認められるようになります。また、商品を手に取ってくれるお客さんたちの中にも商品のストーリーに共感してくれる人が増え、評判が広がり、次第にほかの百貨店からも声がかかるようになります。
さらに、着物の下に着る長襦袢(じゅばん)をTシャツにした「JUBAN Tシャツ®」というアイテムも発表。これは日本の優れた商品やサービスを世界に広めることを目的に創設された「おもてなしセレクション」にも選ばれ、今も国内外にたくさんのファンがいるヒット商品となりました。
こうした新しい商品の販売のほか、15年ほど前はまだ少なかった自社ホームページの作成にもいち早く着手。話を伺っているだけで、そのアイデアや行動力に驚かされますが、すべての原動力は、「このままではいけないという恐怖心と、たくさんの悔しいという気持ち」と話します。

コロナによる更なる危機の中で出合ったのが、捨てるものを使った染物
「JUBAN Tシャツ®」は外国人観光客にも人気が高く、空港などでの取り扱いもスタート。また、店舗で実施していた染物体験も外国人には評判で、たくさんの人が体験をするために訪れるようになります。ところが、2020年から新型コロナウイルスの感染が拡大。観光客が一気にいなくなり、花火大会や成人式など着物を着るイベントごとも減り、着物の需要がさらに少なくなります。
「本当にマズイと思いました。とにかく必死でしたね。何かできることをとにかくやっていかなければと、あの頃は日々動き回っていました」
そんなとき、近くのカフェでコーヒーの出がらしを大量に捨てなければならないという話を耳にします。天然染料についても知識があった野口さんは、「うちにはこれまで培ってきた染めの技術がある。このコーヒーの出がらしを使って新たな染めの商品ができるのでは?」と閃きます。捨ててしまうもので染める「Re COLOR PROJECT」の始まりです。

「捨てるものを使って染物をするというサステナブルな考えは、染め直しや洗い張りをして長く大事に使おうという着物の考え方に通ずるものもあるなと感じました。しかも札幌は全国的に見てもカフェが多い町と言われていましたし、そこにストーリーのある商品が生まれると思いました」
まずはコーヒーの出がらしを使った珈琲染めの生地でポーチやペンケース、ショールなどを作り、これまで取引のなかった雑貨店やセレクトショップなど新しいところへ営業に回ります。さらに、北海道各地のワイナリーのブドウの搾りかすやアロニアの搾りかすを使った染めにも着手します。デニムの着物の販売を始めたときと同様に、ポップアップショップなどでは自ら店頭に立ち、マーケティングを兼ねてたくさんの人たちと対話を重ね、どんなものを求めているかもリサーチしました。
北海道だから作れるもので差異化を。白樺の天然染め「BETULAN」
「よく差別化という言葉を使う方がいらっしゃいますが、私は差別化ではなく、差異化を意識しています。ほかとの明確な違いを出しつつも、優劣で競う差別化ではなく、商品そのものの良さをしっかりと打ち出していけるものを作っていきたいと考えています」
その差異化の極みとなる天然染めの原材料が「白樺」です。北海道で生まれ育ち、北海道の良さを出していきたいと常々思っていた野口さん。北海道だからできること、作れるものを形にしたいと考えていたときに出合ったのが白樺でした。


「北海道の自然景観といえば、観光客の多くの方が白樺の並んでいる情景を思い浮かべると思います。ちょうど蘭越町で天然白樺の樹液を使った化粧品作りを行っている「SIRACA」。山を育てるために間伐をしているということを知り、これだと思いました」
樹皮や枝、葉を譲り受け、白樺を使った天然染めを行うことに。専門家の力も借り、ブランディングを構築するところからのスタートでした。
1年半近くブランド作りにじっくり時間をかけ、2023年に染めのブランド「BETULAN」が誕生しました。コンセプトは、「息吹で、染める」。染めることで、もう一度白樺の息吹をよみがえらせるという思いを込めています。

「アパレルや雑貨ブランドなどから染めのオーダーを請け負うBtoBメインのブランド。まだスタートして間もないので、これから大事に育てていきたいと考えています。うちの工房で染めるので、大手のような大量生産はできませんが、北海道のものを使った天然染めという部分に共感してくれる方たちと繋がりあいながら広げていければと思っています」
実際、すでに道外企業や道内で活躍している個人事業主の方たちとのコラボなども実現。今もいろいろな相談が寄せられているそうです。
どのような色に染まるのか、染めたものを雑貨や洋服にするとどのようになるのか、色や風合いを見てみたいという方のために、工房にある店舗で商品を見ることができます。また、すすきのにある複合商業施設「COCONO SUSUKINO」にある雑貨のセレクトショップ「Idéal.」でも、「BETULAN」の生地から作ったポーチやトートバッグなどを手に取ることができるそう。

染色技術をどう生かして多角化するか。海外進出も視野に入れ、これからも挑戦は続く
こうして新たな染めの挑戦に取り組む傍ら、JUBANTシャツ®の販売に関しても動きがありました。
「コロナ禍にJUBANTシャツ®の販売をクラウドファンディングで挑戦したのですが、それをきっかけにアメリカのクラファンサービスのパートナー企業から、同じようにJUBANTシャツ®の販売をしないかと声がかかり、今年の1月から海外挑戦がスタートしました。コロナ前は北海道に来たインバウンドの方のお土産や体験を通じて商品や着物・染色文化を伝えてきましたが、これからは海外で商品を販売していくことを視野に入れて動きたいと思っています」

常に先を見据えながら考え、積極的に動いている野口さん。「会社を経営していくにあたって、何かのせいにして立ち止まっていてはいけないと思うし、現状維持でもいけないと考えています。私自身、何をやるにも最初からあきらめるのではなく、とにかくやってみて、徹底的にやり切ったほうがいいと思うタイプ。だから悩んでいる暇はないんです」とキッパリ。日本の着物文化や染色文化を次の世代に伝えつつ、自分たちが持っている染めの技術をどう生かして多角化していくかを考えているそう。
また、人との繋がりも大事にしているという野口さんは、「これまでたくさんの人たちに支えてもらいながら事業を進めてきました。自分一人では何もできないし、協力してくれる人たちがいるからこそいろいろなことに挑戦できていると思います」と話します。
2人のお子さんがいる野口さんは、「子どもに誇れる仕事をこれからもどんどんやっていきたいですね」とニッコリ。また、学校教育の場で着物や染色の文化を伝えられる機会があればと考えているそうで、「家で着物を着る人がいないと、着物に触れることもないまま育ってしまうので、世界に誇れる文化があることを若い世代にも知ってもらいたい」と話します。最後に「これからも根っこのコンセプトを大切にしながら、新しいことにも果敢に挑戦していきます」と力強く語ってくれました。