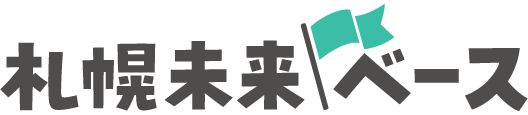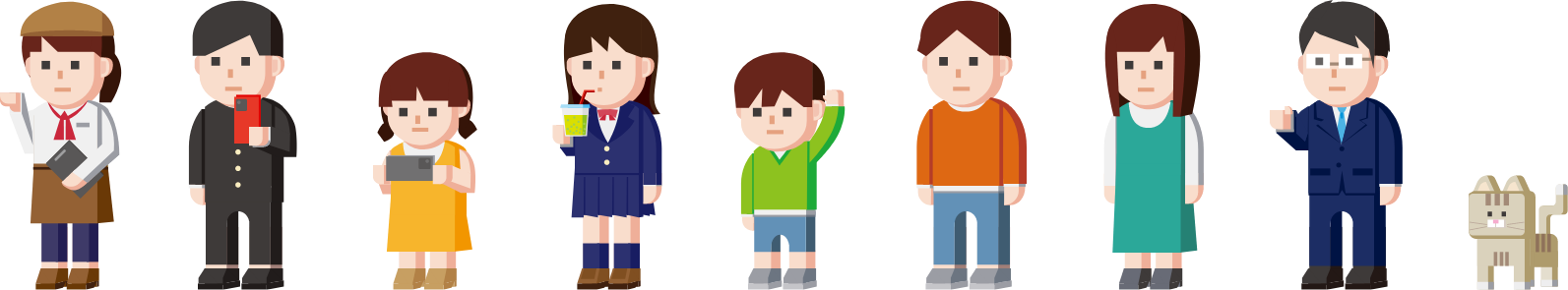フリーランスの編集・ブックライターに加え、「温泉ライター」という一風変わった肩書きを持つ高橋一喜さん。自身の「日本一周3016湯」を巡る温泉の旅を書籍化し、テレビ番組をはじめとするメディア出演の経験も少なくないことから、ご存知の方も多いはずです。2021年には暮らしの拠点を札幌市に移した高橋さん。これまでに至る道のりを伺いながらその理由を紐とき、このまちのこれからについても尋ねてみました。
「分かりやすさが一番」につながった出版社時代。
高橋さんは千葉県のご出身。大学進学に伴い上京し、就職活動では出版業界に狙いを定めていたと振り返ります。
「とはいえ、当時はいわゆる就職氷河期でしたし、出版社をはじめとするメディア関連の企業は人気が高く狭き門。目ぼしい会社は壊滅状態で、恥ずかしながら親に泣きついて就職留年の道を選びました」

これほどまでに出版社への就職を熱望していたのであれば、本好きな少年時代を過ごした…かと思いきや、「本の虫といえるほどの読書家ではなかったんです」といたずらっぽく笑います。中学生のころにはドラマ好きが高じて脚本を書いてみたものの、ご自身が評するに「クソ学園もの」として完成には至らず、絵を描いてみてもモノになる予感は抱けなかったとか。それでも想像することが好きで、とりわけ文章の表現力に惹かれていたため、出版社への就職は譲れなかったといいます。
「二度目の就職活動でようやく内定を得られたのがビジネス書を手がける出版社。この分野は小説のように『著者ありき』ではなく、時流にウケる企画を書籍に落とし込むことが大切です。内容に関しては表現力が高くても難解な文章は読者層に好まれず、シンプルに理解できることが第一。今、僕が分かりやすさにこだわって言葉を紡いでいるのは、少しばかり読みづらい原稿にも数多くふれてきた当時の経験が大きいと思います」

高橋さんが企画したビジネス書の中には、10万部以上のベストセラーもありました。当時(2000年代初頭)の出版業界は深夜でもオフィスに光が灯る時代。高橋さんもご多分に漏れず残業や休日出勤が当たり前でしたが、「体力的に辛いことは辛かったですが、それよりもやりがいや楽しさが上回っていましたね」と懐かしむような視線を宙に向けました。
温泉が放つ個性の数々に、興味の熱が急上昇!
高橋さんは、今でこそ「温泉ライター」として名を馳せていますが、実は子どものころからお風呂嫌いだったと驚きのカミングアウト。温泉にも興味がなかったと率直にいいますが、何がきっかけで真逆の道へと進んだのでしょう?
「出版社に勤めていた時代、和歌山県の南紀白浜(なんきしらはま)温泉に出かける機会がありました…あまり気は進みませんでしたが(笑)。ただ、観光スポットとしても人気の『崎の湯』が、まさに人生を変えるような出会いとなったんです。波打ち際に設けられたダイナミックな露天風呂。大海原と一体化したようなロケーションに、こんなにスゴい温泉もあったのか…と感動したことを昨日のことのように思い出せます」

以来、高橋さんは残業で疲れた体を癒やしに、週末となればあちこちの温泉へと出かけるようになりました。この「湯巡り」を続けることほどなく、興味は「泉質」へと変わっていったそう。何だか化学的で難しそうなイメージもありますが…。
「いえいえ。例えば、同じ温泉地でもA湯は透明なのに、少し離れたB湯はにごり湯というケースも多いんです。もっと極端にいえば、同じ浴室内にもかかわらず、黒い湯と白い湯が共存していたこともあります。そんな一つとして同じものがない温泉の個性に取りつかれました」
「もっと温泉のことを知りたい」「全国を巡ってみたい!」。そんな熱量がグングンと上昇していく一方で、業務は相変わらず忙しく、温泉地を旅する時間も確保しづらい状況。加えて、仕事に対する行き詰まりを感じる中、プライベートの面でも落ち込む出来事が重なり、2008年に一つの決心を固めます。

「会社を辞め、日本全国3000湯を目標に旅に出ることにしました」
「最低30分、1日8湯」の過酷で楽しいノルマ!?
日本全国3000湯を巡る旅の資金は、会社員時代にコツコツと貯めてきた貯金。その金額から逆算し、1日にかけられる予算とともに「巡るべき湯のノルマ」も弾き出しました。それは一つの温泉施設に最低30分は滞在し、1日8湯に入浴するという一般には無謀ともいえる数字です。
「生まれ故郷の千葉から旅をスタートさせましたが、それがマズかったです。土地が広いわりには温泉地が少なく、移動に時間が割かれるのもストレスでした。しかも、初めのうちは体が慣れていなくて、5湯にも浸かると湯あたりする有様。1週間くらい経ったころにキツすぎる…とすでに辞めたくなったり(笑)。ただ、群馬や栃木といった名湯の多い地域に足を踏み入れると気分がどんどん高まり、ポジティブに次を目指すようになりました」

2008年当時は現在とは異なり、インターネットの情報も充実しておらず、当然ながらグーグルマップもありませんでした。高橋さんは湯巡りしたい温泉地にあたりをつけながら、時に行き当たりばったりに看板の温泉マークに導かれたり、時に地元の人に情報を聞いたりしながら、ただひたすらに「1日8湯」を楽しんでいたとか。とはいえ、旅が終わった先のことを不安視しなかったのでしょうか?
「将来についての不安はまったくなかったというのが本音です。出版社時代にフリーランスの編集者やライターに仕事を依頼する立場だったため、今度は僕がそうした形で食べていくことはできるだろうと考えていました。実際、今も出版社の元同僚や、一緒に本を作った著者から声がかかり、ありがたいことに新規の営業をせずとも生活が成り立っています」

結果として高橋さんは386日かけて3016湯を巡りました。前人未到ともいえるこの「極端な経験」が、2014年に出版された『日本一周3016湯(幻冬舎新書)』として日の目を見ることになりました。
唐突な思いつきなのに、移住の条件に合致!
その後、高橋さんはしばらく東京でフリーランスの編集者・ブックライターとして働きました。「温泉ライター」としての仕事はゼロではなかったものの、当初は積極的に取り組みたいとは思っていなかったと、意外なことを口にします。
「好きなもので食べていこうという気になれなかったのが正直なところです。例えば、僕があまり好みではないと感じている温泉について記事を書いてほしいと依頼されると、ムリにでも持ち上げることになります。心から好きな温泉で嘘を並べてしまうことになるのは、やはり気が進まないものですからね」

このような温泉ライターとしての心持ちも含めて生活を一変させたのは結婚と子育て、何より札幌市への移住。折しもコロナ禍でリモートワークが一般的になり、高橋さんの仕事が場所を選ばなかったことも拠点を移す後押しとなりました。
「東京は人も情報も多く、刺激が強すぎることに嫌気がさしてきたころのこと。僕ら家族が住んでいた新宿区の幼稚園に娘を通わせるべきか、妻ともよく話すようになりました。もう少し自然豊かな場所で子育てしたほうが良いのでは…と。加えて、会社員時代と忙しさが変わらず、ストレス過多から抜け出すために温泉に出かけるという入浴をあまり楽しめない状態。出版社の担当者が『原稿、まだですか』と自宅のドアを叩ける物理的な距離の近さも、ゆとりを奪っていたかもしれません(笑)」

高橋さんと奥様が移住先の検討にあたって大切にしていたのはある程度の都市機能と、少し足を延ばすだけで自然にふれられる環境。最初は軽井沢や鎌倉といった関東圏を候補に考えていましたが、ピンとくるまちがなかったそうです。
「僕は真っ先に温泉地の別府を思いつきましたが、全国の温泉を取材する連載を持っていたため、航空アクセスが良くない点から断念しました。そんな時、北海道に足を踏み入れたこともない妻が、唐突に『札幌がいいんじゃない?花粉も少ないし』と(笑)。ただ、よくよく考えてみると都市機能は十分で、各地への就航も多い新千歳空港が近いのは条件にピッタリ。突拍子もないような思いつきが移住に結びつきました」
都市機能と自然環境のバランスが抜群。
高橋さんにとって、札幌市への移住は温泉のことを考える時間の増加に直結しました。それまでの編集・ブックライターの仕事が多少減ったことで、ソロ温泉や温泉ワーケーションといった「温泉の活用」に考えを巡らせられたり、「note(クリエイターのメディアプラットフォーム)」に365日連続投稿することで反響が届いたり、「もっと温泉のことを知ってほしい」と温泉ライターとしての活動に前向きになったと微笑みます。
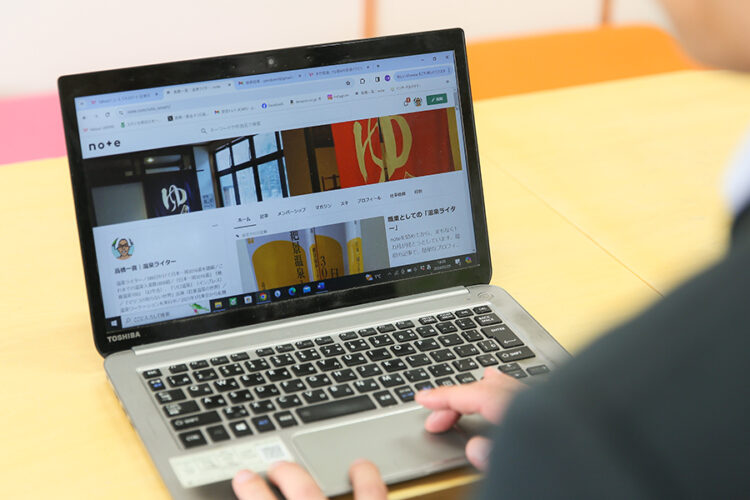
「東京時代に比べて仕事量はやや減りましたが、生活コスト…特に家賃が2/3になり、1部屋増えたので生活の質はグンと高まったと思います。バリバリ仕事をこなさなずとも暮らしは成り立ちますし、夜に温泉のことをしっかりと考えられる時間も増えました。それに札幌は時間の流れがゆっくりと進んでいる気がして、東京では3分後に電車がくるのに駆け込んでいたことに、『なんであんなに急いでいたんだろう』と自分自身で可笑しくなることも」
インタビューの時点で高橋さんのお子さんが通っているのは幼稚園の年長クラス。新宿区で見学したいくつかの園とは異なって定員数も多くなく、担任の先生や友人の顔と名前が一致する適度な規模感だと感想を漏らします。雪の時期には毎日のようにそり遊びを楽しんだり、奥様もママ友と出かけたり、家族も札幌市の暮らしを満喫しているそうです。

「もともと日曜日は仕事を休み、娘と遊ぶ日と決めています。今は近所の公園で自然と戯れられ、大通公園で季節ごとに開催されるイベントを眺めながら一緒に散歩するのが一番の楽しみです。地元に暮らしていると気づきにくいかもしれませんが、都市機能がありながらすぐそこにスキー場があり、クルマで1時間圏内に豊平峡温泉という素晴らしい温泉地があるなど、マチと自然のちょうどいいバランスは他にないと思います」
今後も、温泉の歴史や文化、個性などを多角的に発信し、著書や記事を読んだ人に一人でも多く足を運んでもらうことが高橋さんのライフワーク。温泉文化の未来を支える一助になりたいと表情を引き締めます。最後に「札幌市にはどんなまちになってほしいですか?」と質問をぶつけると、しばらく頭を悩ませた後にこう答えました。

「う~ん…テーマが壮大すぎて僕の口からは何とも(笑)。ただ、身の丈の話題でよければ、教育の質と強度を担保しながら、ゆとりも持てる子育て環境をより進化させてほしいですね」
高橋さんの話しぶりは終始穏やかで、どんな問いかけにも一つひとつ言葉を選びながら誠実に答えてくれました。インタビューを終えた後に胸の内がじんわりと温まったのは、まるで温泉のようにあたたかな人柄にふれた「効能」なのかもしれません。