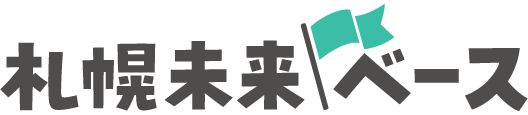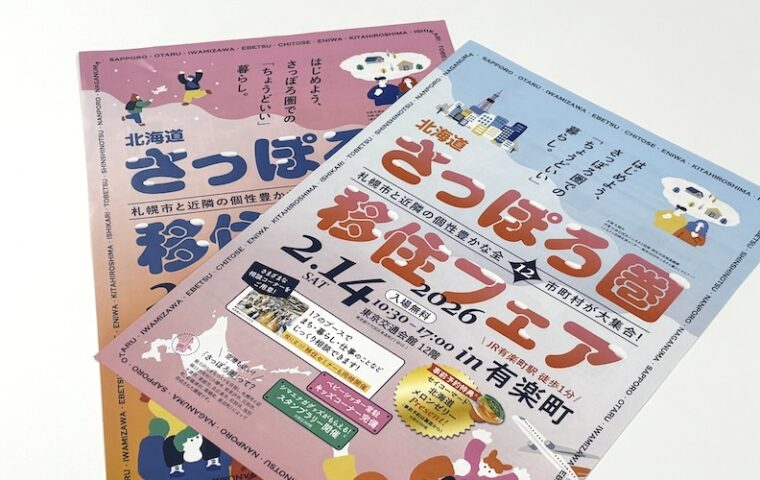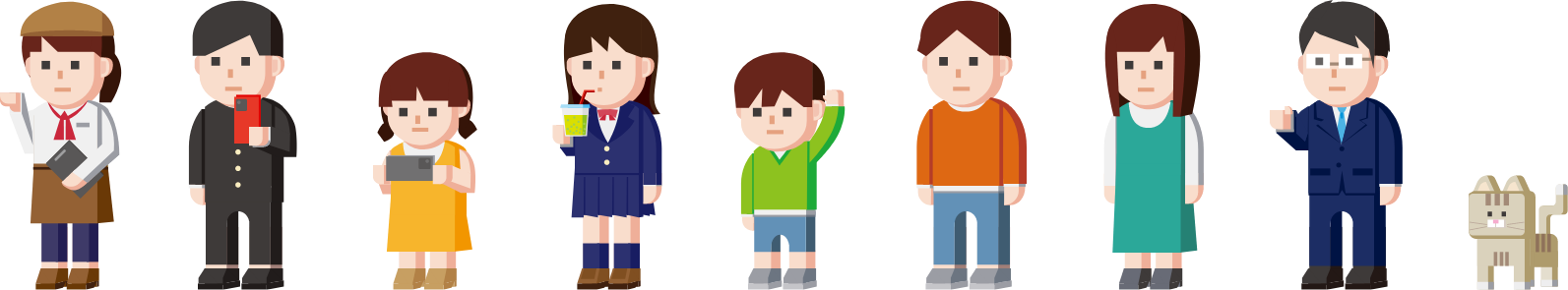北海道神宮の近く、北1条宮の沢通り沿いから住宅街へ入ったところに、今回おじゃました「フーズバラエティすぎはら」があります。初めて訪れる人は「ここにこんなスーパーがあるとは!」と驚くはず。店舗の前の道は、車がすれ違うのもやっとというほど。それでもひっきりなしに車が駐車場へ入っていきます。社長を務める杉原俊明さんは3代目。ここまでくるのには紆余曲折、さまざまなドラマがありました。そんな俊明さんを支えているのは、奥さんをはじめとする家族。10年前からは、長男の一成さんが店の食品部門を担うようになり、俊明さんを強力サポート。俊明さんと、店長の一成さんにこれまでの歩み、そしてこれからの店のことや地域への思いを語ってもらいました。
昭和16年創業。地域のコミュニティーの中心だった杉原商店
建物自体は昭和に建てられたものを改修しながら使用しているそう。どこか懐かしいような、レトロな感じが店の味になっています。店内には、目利きの俊明さんが選んだ野菜や果物、一成さんが仕入れる日配品を含めた食品や酒類が所狭しと並び、札幌の人気の花屋「HANAYASU」の切り花、奥には魚屋と肉屋も入っています。100坪ほどのいわゆる「町のスーパー」の広さですが、ディスプレイやポップにも工夫が施され、一つひとつの商品を見ているだけでワクワクします。


「この建物は先代の父のときに建てたもの。父がしっかりしたものを造ってくれたおかげで、少しずつ改装、改修しながら使い続けられています。頑丈に建ててくれたので、ありがたいですね。古くても磨いてキレイにしていれば長く使えるので」と俊明さん。
「フーズバラエティすぎはら」が、宮の森で杉原商店として創業したのは昭和16年。京極町で雑穀商として事業を成功させた俊明さんの祖父が、そこで築いた財を用いて今の建物の向かい側に米の配給所を構えたのが最初だったそう。ここからは俊明さんに杉原商店の歩みを伺っていきたいと思います。

「祖父は、地域の人から、あれが欲しい、これが欲しいとリクエストがあるたびに、肉屋や魚屋などに声をかけ、しまいには郵便局や交番もこの並びに誘致したそうです。何もないところから、地域のみんなで町を作っていったような時代だったんでしょうね」
創業当時の写真を見せてもらうと、店が立ち並び、賑やかだった様子が伝わってきます。杉原商店の前には街頭テレビが設置され、夕方になると相撲の放送を見に近所の人たちが集まっていた時代もあったとか。お正月には店の前で出初式が行われるなど、杉原商店を中心にコミュニティーが出来上がっていったのが分かります。
「自分も幼いころは、店の周りがとても賑やかだったのを覚えています。でも、1972年の札幌オリンピックの後に地下鉄東西線の開通やバスの路線整備などがあり、人の流れが変わり始めると、なんとなくこの辺りも寂しくなってきたんです」
交通網の変化による人の流れもそうですが、この頃から大型スーパーの台頭、コンビニエンスストアの登場など、小売業の業界にも変化の兆しが訪れます。

「2代目の父が『これからはスーパーの時代だ』と、1975年の9月9日にこの建物を建て、フーズバラエティすぎはらをスタートさせたんです。魚屋や肉屋にも声をかけてここに入ってもらって、集中レジを導入しました。でも、本州から大手スーパーが次々と札幌に進出し、競合が増え、決して楽な経営ではなかったと思います」
世の中に合わせるのではなく、自分本位でいこう。そう振り切るまでの紆余曲折
2代目の父親から「跡を継いでほしい」と言われたことはなかったという俊明さん。大学を卒業後、大手ハウスメーカーに営業マンとして就職します。
「当時は24時間働けますかの熱血会社員が重宝されるような時代。今ならブラックといわれる働き方が当たり前でした。このままだと体がもたないと思って、実家の店も経営が厳しいというのは知っていたけれど、同じ大変なら誰かの下でやるより、自分でがむしゃらにやったほうがいいと思って、会社を辞めて、実家の店に入ることにしました」
俊明さんのメモによると、1988年5月15日、なんとちょうど妻の昭子さんと結婚した日に杉原商店に入社したそう。

「妻もびっくりしたと思いますよ。ハウスメーカーのサラリーマンと結婚したつもりが、じり貧状態の八百屋の嫁になったわけだから」と笑いますが、結婚後、昭子さんは懸命に家業をサポート。それは今も変わらず続いています。
1995年、食品卸の大手・国分グループが100~300坪規模のスーパーチェーンを実験的に行うと聞き、チャンスが訪れたと加盟。売り場を直したり、最新鋭のシステムを導入したりしますが、なんと4カ月でそのスーパーチェーンが解散してしまいます。
「当時は1000坪以上の大型スーパーかコンビニが主流の時代。100~300坪規模は無理だと判断したんでしょうね。それで、また経営診断の相談に行ったんですけど、そこでも『もう無理です』と言われてしまって…」
追い打ちをかけるように、1997年に北海道拓殖銀行が破綻。さらに、近隣にスーパーが増え、中には安売りを前面に打ち出した競合が現れるなど、「客足も減る一方だし、本当にどん底状態の赤字でした」と話します。

「でもね、もうやることはやり尽くしたなと思ったんです。だったら、これからは自分本位でいこうと。世の中に合わせるのではなく、オレオレでいこうと思って、尖がったほうに舵を振り切ることにしたんです。当時、息子たちは小さくてこれからまだまだお金もかかるし、とにかくがむしゃらにやって稼ぐしかないと必死だったというのもありますね」
ここからこだわりの商品を数多く取り扱うようになります。身銭を切って、自身が食べておいしいと思ったものを直接仕入れ、これらは全て買い取り。常に真剣勝負だったと振り返ります。当時小学生だった一成さんは、「いつも大変そうだなと思って父を見ていました」と話します。
師に気付かされた八百屋としての本分
俊明さんの八百屋としての意識を大きく変える出来事がありました。かねてから拓殖大学北海道短期大学の教授で、北海道のクリーン農業の父と呼ばれた野菜博士の故・相馬暁さんとも親交があった俊明さん。あるとき相馬先生に、「八百屋という仕事は素晴らしいね。作り手(生産者)でも、料理や調理をする人でもなく、その両方を繋ぐ橋渡し役なんだから」と声をかけられます。

「でもね、そのころの自分は市場に毎日通っていたけど、野菜のことをまったく語れなかったんです。先生に八百屋は素晴らしいねと言われたけど、そこに自分が達していないと逆に気付かされたんです。そのあと、野菜のことを勉強しなきゃと思っていたけど、なかなかできなくて、2005年3月に相馬先生が亡くなったとき、僕ね、恥ずかしくて先生の葬儀に行けなかったんです」
先生の死をきっかけに、野菜の勉強をはじめようと奮起。日本野菜ソムリエ協会(現在)の講座に通いはじめ、2005年の秋には野菜ソムリエ(現在)の資格を取得します。さらに、その年の10月には北海道フードマイスターの資格も取ります。そして、2007年春に野菜ソムリエプロ(現在)を取得し、やっと相馬先生の墓前に手を合わせることができたそう。
「八百屋の仕事って下に見られがちだったんですけど、相馬先生に川上(生産者)と川下(消費者)をつなぐ仕事で素晴らしいと言ってもらってから、八百屋の地位を自分たちで上げていこうって考えを切り替えることができました。また、相馬先生のおかげで、農家さんとも繋がりができ、本当に感謝しかありません」
祖父の死と子どもの誕生をきっかけに、自分が4代目を継ごうと決意
さて次は、俊明さんの話を横で聞いていた一成さんにいろいろ伺っていきましょう。

いつも忙しそうにしている両親や祖父母を見て育った一成さんは、「子どものとき、父が運転する配達のトラックに乗って、手伝いについていくのは好きでした。一緒にいられて楽しかったんですよね」と振り返ります。「でも、父が祖父から跡を継げと言われなかったように、僕自身も父から跡を継いでほしいと言われたことはなく、自分も継ぐつもりはありませんでした」と話します。
もともと食べることが好きだった一成さんは、大学で経営を学び、卒業後は滝川にある食品会社に就職。物産展の仕事を任され、全国を飛び回っていました。
そして、2015年に杉原商店へ。そのときは明確に「跡を継ぐ」とは考えていなかったそうですが、あるきっかけがあり、4代目を継ごうと決意します。
「2021年の8月に入籍し、そのすぐあとの10月に祖父(2代目)が亡くなり、12月に息子が生まれたんです。祖父の死と息子の誕生を機に、自分が4代目を継承しようと心を決めました」
実は取材日の1週間後には第2子も誕生予定ということで、「いつ生まれてもおかしくないんです」と少しソワソワした様子。「やっぱり子どもができると、今まで以上に頑張らなきゃとは思いますね」と話します。
今は店長として、食品や物販関係をすべて任されている一成さん。一成さんも野菜ソムリエ、北海道フードマイスターを取得しているほか、唎酒師やソムリエの資格も持っているそう。

「店に入ってから取ったのですが、食べるのも、飲むのも好きなので、資格を取るのも楽しかったです。小さな店なので、お客さんから声をかけられることも多く、聞かれたことにきちんと答えられるようになりたいと思って資格は取得しました」
俊明さんから「好きにやっていいよ」と売り場を任された当初は、マニュアルも特にないので手探りだったそうですが、一成さんなりに自分の学んだことやこれまでの経験を活かし、俊明さんとも異なるセレクトで商品を揃えていきました。休みの日にはデパ地下や競合店を見て歩き、お酒の試飲会なども積極的に参加。気になる商品があれば、俊明さんと同じように自分でお金を出して購入し、味を確かめてから仕入れるかどうかを決めているそう。
俊明さんは、「最初は大変だったと思います。とりあえず自由にやってごらんと任せたら、息子の得意を生かした商品選びになっていて、気付いたら自分が仕入れていたものが消えていたことも(笑)。ちょっと寂しく思うこともあるけど、でもやっぱり息子の成長を感じられるのは嬉しい。息子に任せるようになって何年か経ったとき、自分の店なのに、『あ、この店の品ぞろえ、なんか面白い』って思った瞬間があって、もう店づくりも安心して任せられるなと思いました」と話します。
3代目と4代目、親子がタッグを組み、次の時代に向けて前向きにチャレンジ
コロナ禍の巣ごもり需要で業績が一気に伸び、冷凍食品の売り場面積を広げ、レジを増やすなどしたというフーズバラエティすぎはら。「個人商店のいいところは、時代の波に合わせて柔軟に店づくりを変えていくことができる点」と俊明さん。とはいえ、ネットスーパーなどのライバルも増えている昨今、次を考えなければと一成さんと検討しているそうです。店のSNSを担当している一成さんは「PVは伸び続けているので、これをもっと売上に繋げられる何かができればと考えているところです」と話します。

一成さんは、「父が幼かったころの、この地域の賑わいへの憧れのようなものもあります。今は何でも安ければいいという時代でもなく、消費者の買い物の志向や求めているものも変わっているので、時代に合った形で、うちの店を中心にこの地域の賑わいを取り戻していけたらと考えています」と話します。今も毎週土曜にポップアップショップ的に実演販売を行っていますが、建物をうまく活用し、それをもっと進化させたような形で何かできないか模索したいと思っているそう。
「食品や物販は息子に任せられるようになったので、僕はまたあらためて野菜のことをイチから学んでいるところです。気候変動によって作物の生育状況や出荷のタイミングなどが変わってきていて、これまで学んだものが覆された状態なので」と俊明さん。学ぶことを続け、どんな状況であれ常に野菜も食品もおいしいと言えるものを店に並べることを最優先に、お客さんたちにそのおいしさをきちんと伝えていきたいと話します。
俊明さんいわく、一成さんは家では口数が少ないほうということですが、売り場に出て商品について尋ねると、はきはきと一つひとつの商品について説明してくれます。一成さんなりの思いも伝わってきて、「じゃあ買ってみようかな」とついつい買い物かごに商品を入れてしまいます。また、思いが詰まった手書きのポップにも購買意欲がそそられます。

さて、最後に一成さんに俊明さんのことをどう見ているかを尋ねると、「父は周りの60代に比べればすごく若々しくて元気。趣味(スキー)にも打ち込んで、仕事にも前向きで尊敬しています」とニッコリ。それを横で聞いていた俊明さんは、「健康にいいよって野菜を売っている八百屋が元気じゃなきゃね」と照れ臭そうに笑います。
戦中に創業し、激動の戦後と高度経済成長期を経て、その後もバブル崩壊、金融破綻、リーマンショック、相次ぐ大きな自然災害にコロナ…と時代の荒波をくぐりながら、この場所に根を張り、商売を続けてきたフーズバラエティすぎはら。来年で85周年を迎えますが、俊明さんは「息子が4代目を継いでいいよと言ってくれてから、心強い相棒ができたと思いながら店に立っています。これからもいろいろあると思いますけど、常に前向きに息子と一緒にチャレンジしていきたいですね」と最後に語ってくれました。