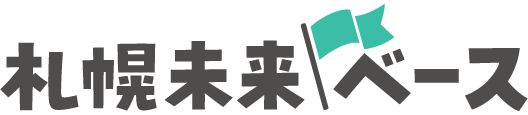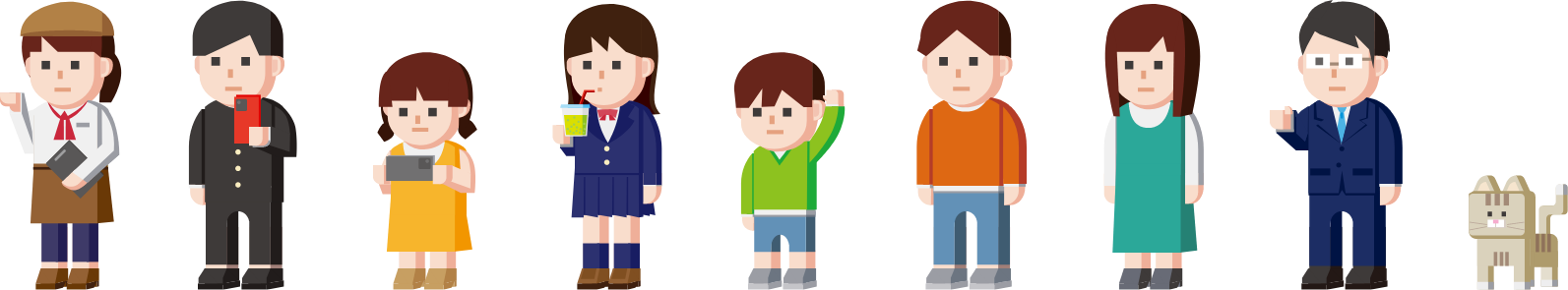札幌市営地下鉄の南北線北18条駅から歩いて3分ほどに店舗を構えるThe St Monica(セントモニカ)。北海道各地の良質な素材を使い、赤ちゃんから使えるスキンケア商品の企画や販売をしている会社です。今回はThe St Monica(セントモニカ)の代表取締役であり、薬剤師の資格も持つ、七戸千絵さんにお話を伺います。女性起業家や母親など、様々な顔を持ちパワフルに活動する七戸さんですが、活動の原点はある人の力強い一言でした。
薬剤師の経験と出産体験から、医療をつなぐ道へ
七戸さんが生まれたのは、札幌。その後、炭鉱の町として栄えていた北海道中央部にある歌志内(うたしない)市で幼少期を過ごします。父は外科医として町の病院に勤務し、母は育児に奮闘する日々。七戸さんの遊び場は、いつも自然の中にありました。

「春はふきのとうや雪解けの土のにおいがして、川では草をすりつぶし色水をつくる。夕闇で見えなくなるまで、全身全霊で遊んでいました」
父親の働く病院は常に忙しく、時には患者の最期に立ち会うこともあったそう。そうした姿を間近で見ながら、七戸さんは幼いながらに「命には終わりがある」ことを知りました。
大学卒業後は、薬剤師として札幌の国家公務員共済組合連合会斗南病院に就職。研究熱心な医師や薬局長のもと、さまざまな診療科の製剤業務を経験しました。ただ薬を処方して渡すだけでなく、患者の歩き方やしぐさから、その人の生活背景を知ることが、ケアの第一歩だということも学んだといいます。

「今思えば、このときの経験が、のちに化粧品を処方する際の基礎になっています」
その後、結婚を機に東京へ移住。七戸さんの人生を大きく変えたのは出産でした。第一子は緊急帝王切開、第二子は子宮破裂という極限の状況での出産。
「どんな形でもいいから、生きて生まれてほしい。その思いしかありませんでした」
壮絶な出産を経験したことで、七戸さんの心には「どんな子どもも尊い」という強い思いが刻まれます。そこで、産後すぐに、カンガルーケアやベビーマッサージ、アロマセラピーの勉強をスタート。夫が多忙な中、いわゆるワンオペ育児をしながら、第二子が1歳を迎える頃には非常勤の薬剤師として仕事にも復帰し、講師業や子育て広場の理事など、複数の活動を並行して行いました。
さらに、産後に身に付けた技術は多くの人の役に立つはずという確信を持ち、都内の総合病院で産婦人科外来主催の教室を開催。福祉施設や保育施設にも活動の場を広げ、アロマセラピーやタッチケアを提供していきます。

「医療をつなぐフィールドで生きることが、自分の役割だと思うようになったのは、薬剤師としての経験と出産体験の両方があったからこそです」
こうした流れの中で立ち上げたのが「The St Monica(セントモニカ)」です。「モニカ」とは、祖母と母から受け継いだ洗礼名。お産で生かされた命を遠くから見守ってくれている、祖母や母への思いが込められています。
起業後は、商店街の空き店舗を活用し、核家族で孤立しがちな母親を中心とした広場事業を展開。活動の幅は徐々に広がり、2008年にはJR線赤羽駅の高架下施設で、核家族の母親と子ども、独居老人が交流する場をつくりました。
「今でいう子ども食堂のはしりです。このときに活動していた団体は、2010年の読売新聞子育て大賞を受賞しました」
The St Monica(セントモニカ)の商品ができるまで

多岐に活動していた七戸さんですが、さらに自社オリジナルブランド「BABY&MOTHER」シリーズを立ち上げます。産婦人科外来のベビーマッサージクラスで使っていた保湿剤を、自分で開発してみないかと声をかけられたことがきっかけでした。
「赤ちゃんの肌に手を添えた時に、その人のぬくもりや気持ちが伝わります。肌ケアに使うものは刺激が少なく、母親の手にも安心感をもたらすものであってほしいと思っていました」
赤ちゃんの肌を保湿しながら、母親自身の回復にもつながる素材とは…たどり着いたのが、北海道美深町産の白樺の樹液です。白樺の樹液には、さまざまなビタミンやミネラル、アミノ酸、タンニン、フラボノイドなど肌に優しい成分がたっぷりと含まれています。この白樺樹液に、国産馬油と蜜蝋をブレンドした保湿クリームを開発。赤ちゃんや母親だけでなく、妊娠中の方にも使いやすいよう、馬油は炭でろ過して無臭にするなど、細部にまで配慮しています。
その後、2010年に東京から札幌へ戻り、飲料や石けん、虫よけ、美容液など、白樺樹液を使用した製品を次々と展開。大手通販事業者やアレルギー対応食品会社の化粧品部門に採用されるなど、販路を拡大していきました。やがて、世間はコロナ禍に突入。七戸さんは、コロナ禍で人の姿が消えた北大構内のポプラ並木を歩きながら、今自分にできることは何かを考えていたそう。

「そのときふと、アイヌの方はこんな時に何を食べるのだろうと思ったんです。きっと良い知恵があるはずだと思い、直接聞きに行きました。そこで教えていただいたのが、シケレベです」
シケレベとは、アイヌ語でキハダの実を意味する言葉。古くから養生食として大切にされてきた食品です。七戸さんは、キハダの実の軽いスパイシーさと抗菌作用が、口腔内の自浄作用を促すのではないかと考えました。そこで、小樽の老舗製菓店に製造を依頼し、北海道科学大学との共同研究を経て誕生したのが「MINAMINAのど飴」です。
「MINAMINA」は、アイヌ語で「みんな笑う」という意味。笑顔が減ったコロナ禍でも、いつかまた笑える日が来るようにという願いが込められています。パッケージにはアイヌ文様があしらわれ、想いと文化を伝えるデザインに仕上げられました。
さらに2023年には藤女子大学とコラボし、学生の提案をもとに、大学の校花である藤の花を使用した「藤バーム」を開発します。この取り組みはコーセーコスメトロジー研究助成を受賞し、2025年に藤学園創立100周年記念事業の寄付返礼品として、「MINAMINAのど飴」とともに採用されました。


若い世代と向き合い、学びを実践につなぐ
藤女子大学では、プロジェクトマネジメント学科の授業も担当していた七戸さん。大学側から依頼され年に数回、「起業」と「ライフスタイルマネジメント」をテーマとした講義を行っていました。
「大学生に自信を持たせてほしい、という願いがあったのだと思います。何かやりたい気持ちはあるけれど、健康やメンタルに自信が持てない子も多い。就職しても、すぐに辞めてしまうケースも少なくないと聞いていました」
そんな学生に向けてフランクに話してほしいという要望を受け、七戸さんは講義を担当。その中で、新たに始まったのが、学生との共同プロジェクト「女性のためのハーブティー」作りでした。発端は、「ハーブティーを作ってみたい」という学生の声だったといいます。
「まず、ハーブ園を探すところから始めなければならなかったので、道内のオーガニックハーブ園をいくつか回りました。その中から、北広島にある黒田ハーブ農園北海道株式会社に協力していただき、原料を提供してもらえることになったんですよね。そのハーブ園のオーナーさんも、藤女子大の卒業生で『学生のためなら』と協力してくれたんです。ハーブティーのデザインは藤女子大の学生が担当し、構成・監修も藤女子大卒業生が行っています」

原料となるハーブを入手した後は、お茶にするための工程が待っています。刈り取ったハーブを剪定し、花と葉だけの状態に整える作業です。さらに、商品が完成した後は、それをどう売るかを考える必要があります。
販売のための資金や場所を確保し、食品の法律を遵守し、利益を生み出すための仕組みまで学生に考えてもらうのが、七戸さんのプロジェクトの目的でした。商品開発や販売の経験がなく戸惑う学生たちをサポートしながら、七戸さんはあえて厳しい言葉をかけることもあったといいます。
「ビジネスの場で、何をして良くて、何をしてはいけないのかを分からない学生は多いです。でも、お願いやお詫びの仕方といった基本的なマナーを学生のうちに身に付けておけば、必ず就職したあとに役に立つと思ったんです」
最終的にこのプロジェクトでは、2種類のハーブティーを製造。学園祭でのプレ販売を経て、北海道ヘルスケア産業振興協議会の展示会で販売し、すべて完売しました。
「正直、完成するまではいろいろな苦労がありました(笑)。ハーブの剪定では、人手が足りず、教授にも手伝ってもらったことがあります。でも、私自身も多くのことを学びましたし、面白い経験でした」
スタートアップの女性起業家を支援
札幌市には、市からの助成金を受け、スタートアップとして事業に取り組む若いママたちも少なくありません。現在、七戸さんは、そうした女性起業家の支援にも力を入れています。
「スタートアップの中で、事業化までたどり着けている人は本当に少ないんです。体感では10%もいないかもしれません。そういう現実を目にして、自分に何かできないかと思っていました」
七戸さんのもとには、看護師や助産師、歯科衛生士など、かつて医療の現場で働いていた人も多く集まっています。そうした人の中には、ボディケアやターミナルケアに挑戦したいと思いながらも、どう始めたらよいか分からない人や、集客ができずに悩んでいる人も多いそう。七戸さん自身、東京で自治体の起業支援制度を活用してきた経験があるからこそ、目の前の女性たちの姿がかつての自分と重なったと話します。

「彼女たちに共通しているのは、やりたい気持ちがあって実際に動いているのに、事業としてうまく回らず、気持ちまで落ち込んでしまっていること。常に模索しているから、心が安定しません。一番大きいのは自分に自信を持てないこと。それが最大のネックです」
では、その自信はどうすれば取り戻せるのでしょうか。七戸さんは「目線を変えれば状況も変わる」と話します。
「例えば、お客さんが集まらないなら、販売ルートや売り方を変えてみる。出口をどうつくるかを一緒に考えています」
一人ひとりの話を丁寧にヒアリングし、その人自身も気づいていない強みを引き出す。七戸さんの助言をもとに、事業の可能性を広げてきた女性も多くいます。
こうした活動の拠点として、七戸さんは現在、札幌市北区北16条にThe St Monica(セントモニカ)の本社を構えています。この場所を選んだのは、「札幌市内でも、大学や教育機関が集まるエリアだから」と語ります。

さらに、七戸さんが理事を務める中小企業同友会HOPEの研究組織のミーティング拠点が、北海道大学構内のFMI(Food & Medical Innovation)にあることも大きな理由のひとつでした。
「この辺りは、産学連携が活発で、経済も循環しやすい場所です。FMIには上場企業も入居しているので、ITを含めた最新の情報が自然と集まってくるというメリットもあります」
自分を頼って来てくれる人がいることが幸せ
地域のママたちのための広場づくりから始まり、自社ブランドの立ち上げやオリジナル商品の開発、女性起業家の支援まで、七戸さんはさまざまな分野に活躍の幅を広げてきました。2025年には、ふるさとである歌志内市のブランド開発にも携わっています。
歌志内市は、日本で最も小さな市といわれ、消滅可能性自治体にも挙げられてきました。しかし2025年、テレビドラマの脚本家として活躍されてきた倉本聰さんが手がける、ドラマの舞台である旧上歌会館(悲別ロマン座)が構成文化財に登録され、炭鉄港日本遺産にも認定されるなど、あらためて市の魅力が見直されつつあります。
The St Monica(セントモニカ)では、アイヌ語で「砂のたくさんある沢」を意味する「ペンケウタシュナイ」というブランド名で、歌志内の資源を生かした石けんとクリームを開発。チロルの湯の温泉水やハチミツ、白樺の樹液、市の指定木であるナナカマドの炭を使用し、炭鉱の町をイメージさせる商品に仕上げています。パッケージに描かれているのは、幼少期に父とスキーを楽しんだ神威岳をモチーフにしたデザインです。

「『ペンケウタシュナイ』の商品化は、薬剤師の経験も生かせていますし、地域にも貢献できている。こんなふうに、自分にしかできない仕事ができたときは、やりがいを感じます」
とはいえ、家庭と仕事の両立は決して簡単ではありません。子どもが小さい頃は育児に追われ、今は親の介護とも向き合わなければならない年代。それでも働き続けられるのは、「好きなことをやっている」という気持ちが原動力になっているからだと語ります。そんな七戸さんの心には、今でも残り続けている言葉があります。
「起業するときにお世話になった中小企業診断士の先生から、『事業をやり始めたら、自由にできるけれど、責任を負うのもすべて自分。だから腹をくくるんだ』と言われたんです。この言葉が私の原点ですね」
起業してから今日まで事業を続けてこられたのは、さまざまな人とのつながりがあったからこそだと語る七戸さん。

「人つなぎって、人から人じゃなきゃできないんですよね。私は自分のことを、人と人をつなぐ自動販売機のようなものだと思っています。会いたい人の名前が書いてあるボタンを押すと、その人とつながれる『七戸ブランドの自動販売機』です(笑)」
一方、The St Monica(セントモニカ)というブランドの未来について尋ねると、少し考えた後で、こう答えてくれました。
「私は、ブランドはモノ。されどモノではないと言っています。私たちが作っているのは確かにモノですが、そのモノを通じて人と人がつながっている。その考え方や素材への思いがきちんと受け継がれていけば、それだけで十分。ほかには何もいりません。今、自分を頼って来てくれる人がいることが、私にとっての幸せです」
薬剤師として、母として、そして一人の起業家として歩んできた七戸さん。その言葉からは「目の前の誰かと向き合う」ことの大切さが伝わってきました。商品開発も支援も、根底にあるのは人とのつながり。その思いは、これからも末永くThe St Monica(セントモニカ)の精神として、受け継がれていくに違いありません。