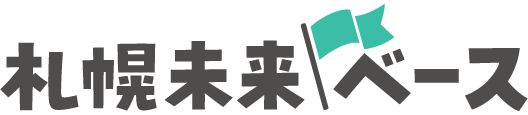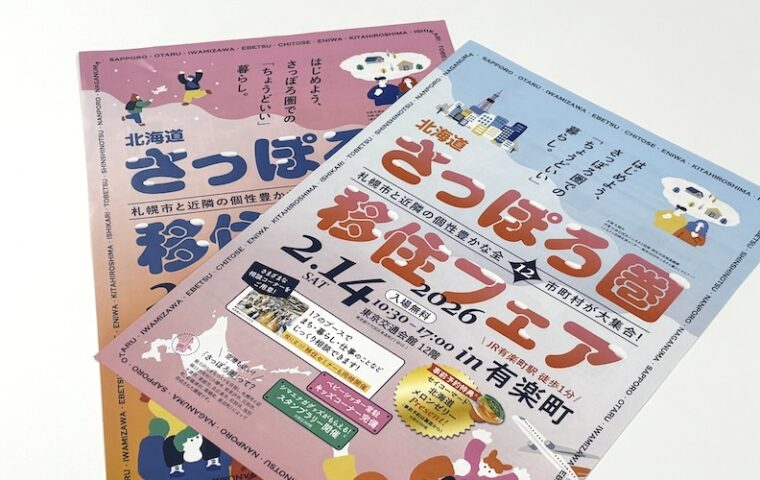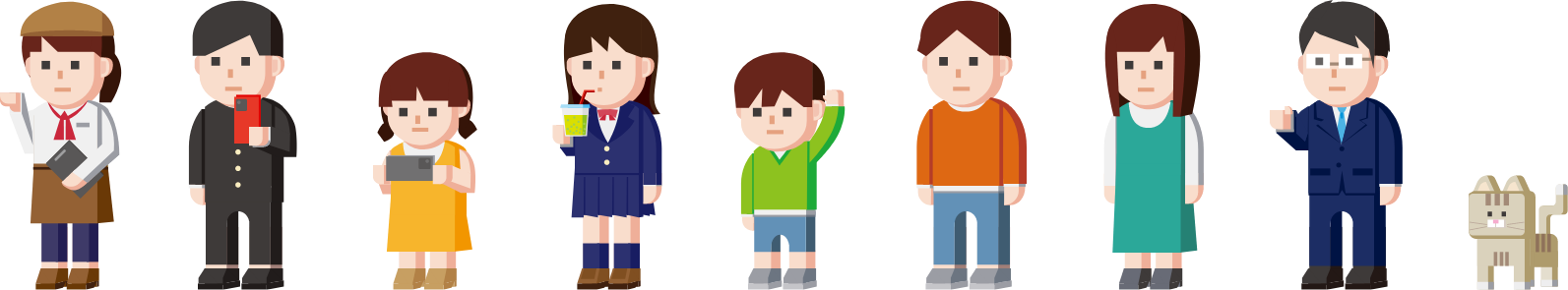「青木征爾 税理士事務所」の税理士、青木 征爾(せいじ)さん。大学卒業後は、大手アパレル会社で販売を経験し、その後税理士となった珍しいキャリアの持ち主です。ただ、税理士になるまでには、血のにじむような努力がありました。なぜ青木さんが税理士を目指そうと思ったのか。またその道のりや税理士になってからの葛藤などに加えて、今税理士を目指している人へのアドバイスなどを伺いました。
大学卒業後、アパレル会社に就職して東京へ
札幌で生まれ育った青木さんが、東京に出たのは27歳のときでした。大学時代からアパレルに関心があり、卒業後はそのまま地元のアパレル会社に就職。最初は札幌の店舗で、販売や接客を担当していました。
働き始めて数年後、会社の人事で東京の店舗へ異動となります。東京での勤務期間はおよそ2年弱。その間に2〜3度の異動を経験し、さまざまな店舗で働いたといいます。東京での仕事は忙しかったものの、手応えも感じていたそう。特定の商品をどれだけ販売できるかを競う全国規模の社内コンテストでは、全国1位に輝いたこともありました。個人としての接客も高く評価され、思いがけず表彰されたこともあったそうです。

「僕は普段、あまり笑わないタイプなんですが、なぜか『笑顔が素晴らしい』とお客さんからコメントをいただいて(笑)。自分でも驚きましたね」
仕事で成果を出し、やりがいも感じていた最中、突然、北海道の千歳市に新しくオープンする商業施設内の店舗へ異動を告げられます。
「理由を聞いたら、真意は別として北海道出身だからと言われました(笑)。最後に配属された店舗はすごく働きやすかったので、できれば異動したくなかったですね」と青木さんは話します。
それでも、青木さんは辞令を受け入れ、再び北海道へ戻ることになります。東京で得た経験や成果を手に、今度は地元・北海道の店舗で新たなスタートを切りました。しかし、東京から千歳の店舗に異動した青木さんを待っていたのは、想像以上に過酷な日々でした。店が閉店した後も、業務が終わらず、残業が深夜に及ぶことも少なくなかったそう。まとまった休みも取りづらく、体力的に大変だったと話します。

「店舗の運営体制的に、僕が頑張らないといけない部分が多かったんですよね。睡眠時間が短くて、店舗が入っている商業施設の定例説明会に行っても話を聞きながら、寝てしまうことがありました」
異動してから2年ほどたった頃、青木さんは少しずつ転職を意識し始めます。理由は、仕事のきつさだったわけではなかったそう。
「本社が東京にあったので、東京で働いていたときは毎週のように本部の人が来て交流していました。そういう関わりが北海道ではなくて、社内とのつながりが狭くなったと感じてしまったんです」
さらに、当時は店長のポストも空いておらず、昇進の見込みがなかったことも大きな要因だったと話します。
「このままここにいたら、慣れた仕事を繰り返すだけになる。それでは年を重ねたときに、悔やむかもしれないと思ったんです。それなら、何か新しいことに挑戦してみようと思いました」
仕事を辞めて税理士試験の勉強に専念し、資格を取得
転職を考えるようになった青木さんが目を向けたのは、税理士という資格でした。きっかけは、ある経済評論家が語っていた「現代の三種の神器は英語・IT・会計」という言葉だったといいます。

「英語を今から学ぶのはちょっと難しい。ITは仕事で使っていけばある程度覚えられる。じゃあ会計は?って。アパレルは商売だから、少し会計と近いかもと感じて、なんとかなるんじゃないか。そう思って、会計の先にある税理士を目指すことにしました」
当時見ていた学校のパンフレットの、「働きながらでも取れる」「早ければ3年で合格できる」といった文言にも背中を押されたといいます。そして、青木さんはアパレル勤務の傍ら、まず簿記の資格を取得。会計事務所に転職し、税理士の補助業務に就きました。
しかし、未経験の青木さんにできる仕事は限られています。しかも、十分な知識がないまま仕事をこなすことに、不安を感じるようになりました。
「このまま続けたら、いつか大きなミスをするかもしれないと思い、1年も働かずに退職しました」
そこから2年間、青木さんは無職になり予備校へ通い、税理士試験の勉強だけに専念する道を選びます。
青木さんは2年間で、税理士の資格取得に必要な5科目の試験のうち、4科目をクリアしました。残る1科目は、新たに転職した会計事務所で働きながら、3年かけてようやく合格にこぎつけたといいます。

「厳密にいうと、無職だった最後の1年もその1科目の勉強をしていたので、合計4年かかったことになります。働きながら資格を取得するのは本当に大変でした」
税理士試験には体力が必要だと青木さんは語ります。制限時間は2時間。丁寧に解けば3時間かかるような問題を、時間内に正確に書き切ることが求められます。
「とにかく早く書けて、正確に暗記できること。この2つがそろえば合格が近づきます」
通っていた予備校では、模試の成績が上位2〜3割に入れば合格圏内とされていたそう。しかし、青木さんはわずかにそのラインに届かない成績が続いていたといいます。
「僕の戦略は、とにかく部分点を拾いにいくことでした。誰もが正解するような基本問題は絶対に落とさない。逆に、9割の人が正解できない問題は間違えてもしかたないと割り切って勉強していました」
最終的にすべての試験に合格し、税理士の資格を取得した青木さんは、その後すぐに転職。事業承継のコンサルティングを専門とする会計事務所に移ります。
「青木征爾税理士事務所」を開業
転職後、青木さんは、税理士として事業承継や相続に関する業務に携わるようになります。
「前の職場では、そういった高度な仕事は担当させてもらえなかったので、自分にとって良い経験になりました。今でもそこで身に付けたスキルは自分の強みになっていると思います」

しかし、徐々に、自分がやりたい方向とは少し違うと感じるようになった青木さんは、次の一歩を踏み出すことを考え始めます。ただし、今回青木さんが考えたのは、他の会計事務所への転職ではなく独立という道でした。
「前職はとても良い会社だったので、それ以上の職場は、もう見つからないのではないかと思いました。大手の会計事務所に行くという選択肢もありましたが、大きな事務所で働いたからといって、必ずしもスキルが身に付くわけでもない。なぜなら、税理士は属人性が高い仕事だからです。それに、僕は自由にいろいろやりたいタイプなので、担当する仕事を縦割りで決められるのが苦手なんです。だからもともと大手には向いていない。年齢的なことも考えて、独立することを決めました」
こうして、2022年9月に、青木さんは自身の税理士事務所を立ち上げることになります。独立当初、青木さんがビジョンとして掲げていたのは、地域貢献と新規事業への支援でした。それまで勤務していた会計事務所で事業承継に携わる中、地方都市を訪れる機会が多く、錆びついていく街の様子に危機感を覚えたといいます。
「地域経済を守る手段のひとつとして、事業承継があるんじゃないかと思っていました。だから当時は、地域のために何ができるかを真剣に考えていたんです」
ただ同時に、何をもって地域貢献と呼ぶのか、自身が顧客に対してどのような価値を提供できるのかという問いにも悩んでいたと話します。

「自分の中では、なんとなく『顧客の経営をサポートすること』というイメージを持っていました。そんなとき、毎年業績が安定しない顧客がいて、自分はその人の経営をまったくサポートできていないと感じたんです。その人を支えるにはどうすればよいかを考えたときに気付いたのが、資金繰りの重要性でした」
税務顧問として融資やIT効率化をサポート
青木さんが現在力を入れているのが、融資サポート・相続業務・IT効率化の3本柱です。企業の法人税や所得税の申告といった税務業務を担う税務顧問の一環として、融資やIT効率化のサポートに対応しています。

「融資サポートでは、事業計画の作成支援や決算の組み方のアドバイスのほか、必要に応じて顧客と金融機関へ同行することもあります。IT効率化は、クラウド会計ソフトの導入や運用のサポートですね。帳簿の入力方法など、実務的なアドバイスも行っています」
一方、相続税は、通常の税務顧問の業務とは別で、スポット的に依頼を受けることが多いといいます。
「相続は、急に必要となることが多く、スポット対応が難しい税理士事務所もあります。しかも、納税額が大きくなるケースもあるため、どちらかというと難易度の高い業務です。ただ、僕は前職で多くの相続業務を経験していたので、その点では慣れていると思います」
顧客の年齢層や業種はさまざまで、集客は知り合いからの紹介やホームページ経由など多岐にわたります。すべての顧客に対応しているのは、もちろん青木さん本人。
「スタッフが多い税理事務所の場合、例えば法人税の話をしていたときに相続の相談がでると、いったん持ち帰って別の担当者に引き継ぐこともあるんです。でも、僕は一人でやっているので、それがない。そこがうちの強みだと思います」
税理士として日々さまざまな相談を受ける中で、どのようなときにやりがいを感じるのか尋ねてみると、青木さんは少し考えてから、こう語ってくれました。

「当たり前のように頼っていただけると、やっぱりうれしいですね。困っていることを素直に『困っています』と言ってもらえるのは、ありがたいことだと思っています。税務とは直接関係のない相談を持ちかけられることもありますが、答えられる範囲であれば、できるだけ力になりたいという思いは常にあります」
一方で、一人で事務所を運営しているからこその大変さもあるといいます。
「すべてを自分でやらなければいけないところですね。当たり前のことですが、雑務も含めて全部が自分の仕事になりますから。ただ、余裕を持って丁寧に対応するためにも、なるべく仕事を詰め込みすぎないようにしています」
目的を決めたらゴールに向けてやり切るだけ
今後の展望について尋ねると、「今ある仕事をきちんと続けながら、自分が提供できる価値を高めていきたい」と答えます。
キャリアチェンジを成功させ、自身の事務所を開いても奢ることなく、実直に顧客のサポートに注力する青木さん。
ここで、税理士にはどのような人が向いているのかも聞いてみました。まずは試験に受かるための条件について、青木さんはこう話します。
「やはり、しっかり勉強することですね。僕の経験から言うと、働きながら試験を受けようとするなら、昼休みなどのわずかな時間も勉強に充てるぐらいでなければ合格は難しいと思います。仕事をしながらだと時間の確保が大変ですが、通勤時間などを使ってコツコツ積み上げていくことが大切です。それから、これは完全に僕の統計ですが、朝ごはんをしっかり食べている人の方が合格率が高い気がしています。税理士試験は、膨大な知識を覚えて挑まなければならないので、思っている以上に体力が必要なんです」
また、自分なりの攻略法を持っておくことも大切だと話します。青木さん自身は、どのように勉強を進めていたのか聞いてみました。

「僕は、とにかく毎日勉強しました。税理士試験より難易度の高い資格を取ろうとしている人は、本当に朝から晩までフラフラになるまで勉強しているんです。そういう人を見ていたら、毎日勉強するなんて、当たり前なことだなと思って。だから、試験当日までは一日も休まずに勉強しました。だって、試験が終われば勉強しなくて済むわけですから、そこまで頑張ればいいだけです。試験に落ちたときは、集中力を維持するために、3カ月間しっかり休んでから勉強すると決めていました。僕は、ただやみくもに続けるのは苦手ですが、ゴールが決まっていれば頑張れるタイプなんです」
最後に、税理士を目指す人に向けてアドバイスをお願いしました。
「まずは、なぜ税理士になりたいのかを自分の中で明確にしておくことが大事です。理由は何でも構わないと思います。例えば、親の事業を手伝いたいという目的でもいいですよね。自分の中にしっかり理由が決まっていれば、それがモチベーションになって勉強も頑張れると思います」
さらに、青木さんはこんなことも話してくれました。

「日本には税理士が約8万人いるんです。なろうと思えば、誰でもなれる職業だと思います。僕からすると、甲子園に出たりJリーガーになったりする方がよっぽど難しいですよ。それに比べたら、税理士になるためのハードルはそこまで高くない。僕みたいに、いったん別の仕事をしながら資格取得を目指すのもありだと思います。税理士の顧客には、一般企業の経営者も多いですから、一度社会に出て基本的なビジネスマナーを身に付けておくのもおすすめですよ」
税理士というと堅い職業のイメージがありますが、青木さんはとても親しみやすく、カジュアルな語り口が印象的でした。「資格試験の最後の1科目だけめちゃくちゃ時間がかかってます」とお話ししていましたが、仕事と勉強を両立させながら資格を取得した粘り強さには思わず「すごい!」と声が出そうになります。「ゴールが決まっていればやり切れる」という言葉にも、力強い意志を感じました。